2025年度 若手向けイベントの報告
若手向けイベント「分岐点で考える、幅を広げるキャリア・一社を深めるキャリア」を実施いたしました!
2025年9月2日開催
対象年齢40歳以下、参加費3000円。若手が気軽に集まれる、敷居の低いイベントを目指して
東京支部では、去る2025年9月2日に若手向けイベント「分岐点で考える、幅を広げるキャリア・一社を深めるキャリア」を実施いたしました。
シニア層が多く、参加費も高額で参加のハードルが高い。そんな同窓会のイメージを払拭し、若手参加者が気軽に集まれるイベントを目指しました。
なお、参加費については、東京支部の有志の会員の皆様から寄付いただいた援助金をあてることで、若手にも参加しやすい価格設定が可能となりました。
ご協力をいただいた皆様には、運営メンバー一同、深く御礼申し上げます。
京都大学経済学部同窓会では、若手参加者の割合が低いことが課題となっています。
それぞれ素晴らしいキャリアを積み上げている京大経済学部の先輩、後輩達と交流できる同窓会の場は、学びの多い貴重な機会です。ぜひもっとたくさんの若手の方に参加してもらいたいという思いが運営陣にありました。
そこで、同窓会運営の若手メンバーを中心に、若い方の「こんなことが学びたい」「こんな人と出会いたい」を叶えられる場にすべく、今回のイベントを企画しました。
今回は、2010年代卒の、比較的若い現役ビジネスリーダー6名にご登壇いただき、パネルトーク形式で若手参加者との交流会を実施しました。
イベントタイトル通り、幅広いキャリアをお持ちの方から1社で長く活躍されている方まで、様々なキャリアの在り方に触れられる貴重な機会になったと思います。
若い方がたくさん集まり、カジュアルな雰囲気でイベントスタート
イベント約1カ月前の7/31情報を解禁、Facebook、LINE、メールで集客を開始しました。
どれだけの方が参加くださるか不安もあったものの、申込期限の8/22には、37名もの方が申込みをしてくださいました!
広報にあたっては、京都の同窓会本部からも卒業生向けLINEに告知・プロモーションをしていただきました。
ご協力をいただき、本当にありがとうございました。
イベント当日、会場である虎ノ門ヒルズビジネスタワー4階「ARCH CAFE & BAR」には、開始時刻の30分以上前から何名もの参加者・運営メンバーが集まり、談笑に花を咲かせていました。
会場のカジュアルで開放的な雰囲気も手伝って、今日はきっと楽しいイベントになる、と確信しました。
お仕事の都合等で遅れる参加者が複数いたため、5分だけ時間を遅らせてのイベントスタート。
 |
柄澤 康喜氏(1975年卒、経済学部同窓会東京支部長)の主催者挨拶をいただいた後、まずは登壇者紹介です。
今回の登壇者は、2010年卒・三井住友海上火災保険所属の俵谷氏、2012年卒・三井住友銀行所属の長野氏、2012年卒・住友商事所属の室氏、2013年卒・ナウキャストCEOの辻中氏、2015年卒・ワールドフィット取締役の東氏、2017年卒・カンフォーラキャピタルCEOの竹中氏の6名です。
現在在籍されている業界も様々ですが、証券会社や大手コンサルを経験された方、銀行を経験された方や、新卒時から一貫して同一事業を深く担当されてきた方など、幅広いバックグラウンドを持つ方にご登壇をいただきました。
 |
距離の近いパネルトーク、議論や質疑応答が白熱
東 邦彦氏(2015年卒、(株)ワールドフィット 取締役)
東氏のテーブルは、東氏の経歴のお話から始まりました。東氏は 銀行、コンサルを経て、当時まだ小さかったパーソナルジム事業に辿り着き、そこから事業拡大して年少50億を達成するまでの変遷について語っていただきました。当初、儲かるフランチャイズ店や直営店を分析し、「量産できる」と確信したそうです。成功要因として、代表の先見性や求人ブランディングも挙げられました。初期段階から上場や売上1000億、1兆円を目指す壮大な目標を掲げるとともに、事業を通して哲学で語られる道徳性や、愛情を持って事業を育てることの重要性が強調されました。
また、質疑応答も非常に活発で、以下のようなやり取りがなされていました。
Q. ジム事業に興味を持ったきっかけと、仕事に対する価値観は?
A. 元々健康に興味があったことと、仕事に裁量と道徳性が必要だと感じたためです。東洋哲学における愛情を持って育てるという価値観が昔から好きで、従業員と向き合いながら仕事ができるのが良いなと感じて今の仕事に辿り着きました。
Q. ジム事業の再建に際して、どのような勝算があったのか?
A. 儲かっている店舗とそうでない店舗を分析し、量産できるモデルを明確化しました。代表の先見性や求人ブランディングも成功要因だと思います。
Q. 入社時にこの仕事に決めた判断は、ロジックと感情のどちらが優位だったのか?
A. 「感情100%」でした。また、仕事をしていく中で「これなら立て直せる」という確信がなければ動けませんでした。代表の前向きな姿勢だけでなく、自分自身でもなんとかできる・なんとかやる・お金が尽きてもどこかから借りるという覚悟はありました。
 |
長野 弘和氏(2012年卒、(株)三井住友銀行 所属)
長野氏のテーブルでは登壇者含め5名にて、アットホームな雰囲気で座談会が始まりました。長野氏は法人営業から経営企画部に異動されているため、異動の理由や経営企画部での業務内容などについて参加者から質問が寄せられました。
特に ANA の予算管理業務を扱っている方が、メガバンクの経営企画部の業務領域の広さに驚いているのが印象的でした。また法人営業と経営企画部が、 経営課題を解決するという意味では本質的に同じことをやっている、と仰っていた点も興味深かったです。
参加者の一人が 登壇者と同じく予算管理に関する部署に所属しているため、 メガバンクの経営企画部における予算管理の考え方や業務範囲について興味深くお聞きになっていました。 長野さんが ご丁寧に質問に対して回答してくださり、終始和やかなムードで座談会は進行していました。
質疑応答の一部を以下にピックアップいたします。
Q. 法人営業から経営企画部に移動したのはご自身の希望か
A. 自身の希望である。 元々全社的な経営方針を定めていく経営企画部に興味があった。
Q. 経営企画部ではどの様な業務を行なっているか
A. 自社の予算策定やコントロール、 中長期の経営ビジョンの策定など多岐にわたる業務 を行なっている
Q. 法人営業から経営企画部に異動したことで、 業務内容はどの様に変わったか
A. 経営課題を解決するという意味では、本質的に一緒である。 法人営業では得意先の財 務状況などを改善することで経営課題の解決に取り組み、 経営企画部では自社の中長期的 な経営の方向性を定めていくことが役割となる。
 |
俵谷 直径氏(2010年卒、三井住友海上火災保険(株) 所属)
俵谷氏のテーブルでは、登壇者を含む 4名にて、和やかな雰囲気の中で座談会が始まりました。最初に行われた自己紹介では、三井住友海上火災保険に長く勤務されてきた経験を踏まえ、今後も他社へ移る考えはないという強い意思を感じさせる発言がありました。 また、 「ワークライフバラ ンス」を重視したキャリアパスを想定されており、座談会の中でもその点に触れられ、 家族を大切にされる一面がうかがえる内容となっていました。 一社に深く根ざしたキャリアを築くという点において、非常に芯の通った歩みをされているという印象を受けました。
参加者の一人は現職が人事部の方であり、 昨今の人材削減の潮流を踏まえ、 人事部の視点と世間一般の視点 の双方からどのように対応すべきかに強い関心を寄せておられました。 その質疑をきっかけに議論は参加者自身を含めたキャリアパスの考え方へと展開し、 非常に充実した時間となりました。 長年にわたり一社に勤めてこられた俵谷さんのお話について、 参加者の皆様は 大変興味深く耳を傾けておられました。
俵谷氏の専門領域について、以下のような議論が展開されました。
Q. 保険会社は人材削減傾向にあるのか?
A. おそらくどの業界も削減傾向にあるはず。 保険会社も例外に漏れないと思う。
Q. もし人材削減を実施するなら、その方法は?
A. 公募と早期退職の2つになると思う。ただ、世間の風当たりも十分考慮しなければいけない。
Q. ぶっちゃけ年収は高いか?
A. 金融業界は比較的高い傾向にあると思う。
 |
室 光誠氏(2012年卒・住友商事(株) 所属)
室氏のテーブルでは、本社での事業投資、 タイへの駐在、日本でのテレビ通販会社へ の出向という室氏の3つの経験の深掘りと、現職に関わる今後の業界見通しが話題の中心でした。 タイ駐在については、日本と現地での価値観の違い等様々な苦労がありながらも、それを乗 り越えてきたとのお話があり、 タフだが意義深い経験であったことが伺えました。
参加者のうち数名が以前からの知り合いであったこともあり、非常にアットホームな雰囲気でした。 メディアやテクノロジーに関わる参加者がいたことから、 質疑はキャリアにとどまらず業界動向にも発展し、 非常に充実し た時間となりました。 事業投資、 駐在、 出向と様々な立場で仕事をされてきた室さんのお話 に、 ご参加の方々は大変興味深く耳を傾けておられました。
Q. 複数の経験をされてきているが、それぞれどう結びついているか?
A. タイ駐在では TV 通販のオペレーションの構築を担当した。 いま出向している会社にも 共通する部分があり、役立っている。 また、 駐在中に想定外の出来事をいくつか経験したこ とで、不確実な状況への許容度が高まった。
Q. 日本発の AI 事業の可能性をどう考えているか?
A. 日本では、AI技術そのものの開発よりも、 どう導入・活用するかのほうが可能性があると感じる。 AI活用を上手にパッケージ化できれば、世界でも展開しうるかもしれない。
Q. TV 通販市場の現状は?
A. 緩やかに伸びている。
 |
竹中 佑旗氏(2017年卒、カンフォーラキャピタル(株) CEO)
竹中氏のテーブルにおける座談会の話題の中心は、竹中さんのキャリアの変遷とキャリアチェンジ時の考えについてでした。 元々、 学生時代から”バイサイド" (株式を運用する側) を志向していたものの 新卒で入れる会社がなく、 まずは外資系証券会社のセルサイドアナリストに なられました。 その後、バイサイド側である投資運用会社に転職、 業務経験する中で、ご自身で会社を経営してみたいと発起し、ファンド設立に至ったとのことでした。
ご参加者のお一人は(竹中さんのファーストキャリアと同じく) 現職がエクイティ・アナリストの方で、 まさに竹中さんのプロフィールをご覧になって、今回のイベントにご参加頂いた、とのこと でした。 そのご参加者からの質疑を中心に、 竹中さんの過去のキャリア変遷を深堀りさせて頂きました。 竹中さんが、 その時々、どういった考えでキャリアチェンジを行ったのか、ご参加者の皆様、大変興味深く話を聞いておられました。
交わされた質疑応答の一部をピックアップいたします。
Q. なぜ新卒で入社した JPモルガン証券から投資運用会社に転職したのか。
A. 学生時代、 株式の運用に関するゼミにも所属していた。 ”セルサイド”よりも”バイサイド”側に関心はあったが、当時新卒で入れる会社がなかった。JPモルガン証券でセルサイドアナリストを経験の後、当初より志向していたバイサイド側 (投資運用会社)に転職した。
Q. 2社目で入社したみさき投資から Janchor Partners へ移った経緯は何か。
A. みさき投資では、マネジメント向けのプレゼン資料のようなワークが多く、 投資業務 の方に時間をかけたいと考えたため。
Q. その後独立され、ご自身でファンドを設立するに至った背景は何か。 自身で会社を設立 するのではなく、企業の経営戦略部といった部署で業務をする選択肢はなかったのか。
A. 雇われの身で業務を行っても、 "経営”についてよくわからないと考え、自身で会社を 経営してみたかった。 自社でファンド業務を行えるようにするため、 どのようにしてミドルバックの体制を整えるか、とても考えた。
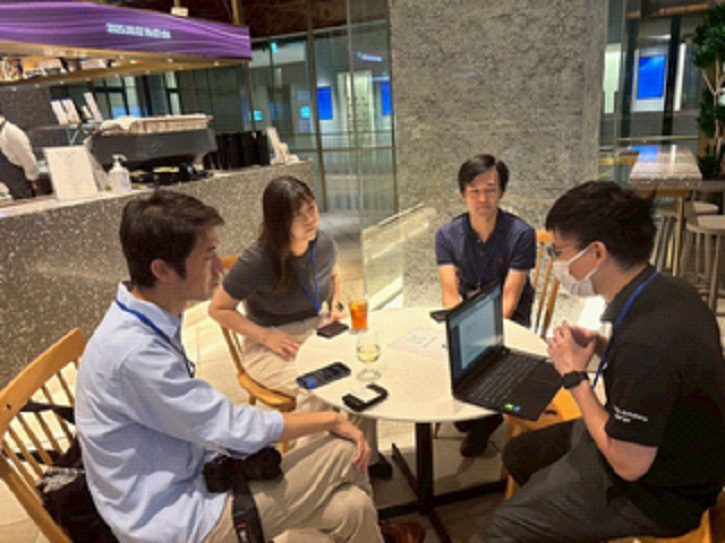 |
辻中 仁士氏(2013年卒、(株)ナウキャスト CEO)
辻中氏のテーブルでは、参加者を含む全員の名刺交換と、お互いの業務内容や経歴についての自己紹介から始まりました。辻中氏は日本銀行でエコノミストとして、統計作成や国会対応の業務に従事されていましたが、将来は企画にいきたいという展望があったこと、日本銀行での業務はマニアックであり、今後のキャリアへの役立ちが不明であったことから転職をされた経験をお持ちでした。
参加者の中にも転職経験者や転職を検討している方がいたこともあり、辻中氏の転職のキャリア選択を中心に議論が展開していきました。
以下のような質疑応答が交わされました。
Q. 転職をする際に必要な能力についてどう考えられているか?
A. 自分はデータを扱った経験がそのまま活きたように思う。転職先ですぐに使える業務経験がないとNGということではなく、必要スキルと経験が被っている部分を糊代にして、スキルを広げていくことができると思う。
Q. 新人として成長していくために、どのような姿勢でいるのが良いか?
A. いきなり希望する職種に就けなくても、まずは自分がタッチできた領域について深く・広く知見を集め、極めていく姿勢が重要だと思う。
 |
集合写真と懇親会、楽しい時間はあっという間
パネルトーク後は、写真撮影をして1時間の懇親会を行いました。
来賓、登壇者、参加者、企画メンバーが、それぞれ好きに食事を楽しみながら交流を行いました。
転職や今後のキャリアについての相談や、パネルトークの時間内に聞けなかった質問、大学時代の思い出話に花を咲かせているグループもあり、和やかながらも活発にディスカッションが行われる、非常に貴重な機会となりました。
終了時間になっても名残惜しく、会場の撤収時間ギリギリまで立ち話をするグループが複数あるほどの盛り上がりを見せた今回のイベント。登壇者、参加者、関わっていただいたすべての方にとって、学びと出会いとリフレッシュの場になっていれば幸いです。
 |
最後に、今回のイベント開催にご協力くださったすべての皆様に深く感謝いたします。
同窓会も若手向けイベントも、これからも引き続き開催予定ですので、乞うご期待くださいませ!
渕上ひなの(2021年卒)


